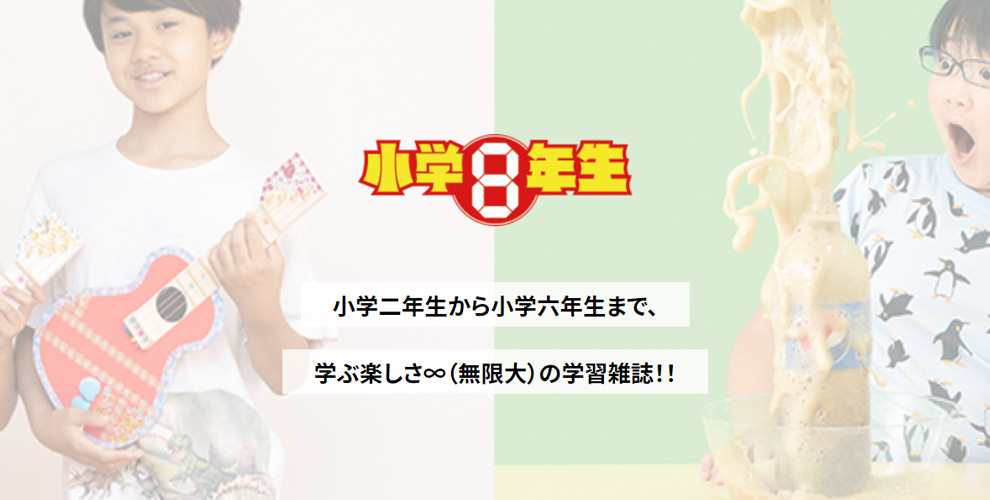コーポレート・アイデンティティを生かした取り組みの体験付録化で、社会へのタッチポイントを増大! 株式会社三越伊勢丹/『小学8年生』のコラボ事例をご紹介
2025/03/28
目次
付録となった包装紙を使って、日本独自の文化である「包む」を体験
三越伊勢丹グループの三越が、全学年向け学習雑誌『小学8年生』とコラボレーションした事例を紹介します。
2024年2月発売の『小学8年生』進級チャレンジ号では、体験付録として「三越〝華ひらく〟小8バージョン包装紙」を企画し、スペシャル包装紙と専用のお包みボックスの紙付録、4ページの特集記事、表紙掲出の内容で展開。日本独自の「包む」文化やデザインについて学び、実際に「包む」体験ができる企画は、好評を博すとともに、その意義が高く評価され、同年9月に発表された日本雑誌広告協会主催の第66回「日本雑誌広告賞」タイアップ広告部門金賞ならびに全部門から選ばれる最高賞(グランプリ)である経済産業大臣賞を受賞という快挙を成し遂げました。
そこで、この企画を推進した広報・PR担当の岡田圭子さんと、メディア企画担当の加藤未知さんに、コラボの経緯や反響などをお聞きしました。

子どもたちへの教育プログラムを「より広く」届けるために
今回のコラボは、三越伊勢丹グループが三越創業350周年を機に実施した「みんなでつくる華ひらく 共創包装紙教育プログラム」を体験付録化したもの。このプログラムは地域社会と連携し日本文化の振興を目的として、三越店舗のある地域の小学校や特別支援学校など全国6拠点で2023年6〜9月にワークショップを開催。日本独自の「包む」文化に込められた〝相手を慮る様式美〟や、自然の造形美をモチーフとした「デザイン」の力についての授業の後、子ども達がグループごとに包装紙をデザインし、制作した包装紙は開催地の三越店舗にて期間限定で使用されました。
「教育プログラム起案のきっかけは、創業350周年を記念してPRとして何ができるのかを考えたことでした。350周年は当社にとっては大きな節目ですが、社会的話題にはなりにくい。それを社会に広めていくにはどうしたらいいかという課題がありました。そこで社が長年培ってきた文化、アイデンティティと教育を掛け合わせれば、生活者の皆様に関心を持っていただけるのではと。当社が長い歴史の中で育んできたものを、教育という形で社会に還元し、そうした取り組みをマスメディアにパブリシティとして報道してもらえれば、より多くの方に知っていただけるのではないかと、プロジェクトが立ち上がりました」(岡田さん)
スキャパレリレッドという独特の赤と抽象的なデザインが印象的な、三越の〝華ひらく〟と名付けられた包装紙は、強力なコーポレート・アイデンティティ。贈り物を美しく包むという文化の中で長年大切にされてきました。
「華ひらく包装紙は1950年に日本の百貨店初のオリジナル包装紙として誕生しました。画家の猪熊弦一郎さんが浜辺の石をモチーフにデザインし、mitsukoshiの書き文字は当時三越の宣伝部社員だったやなせたかしさんによるものです。戦後のまだ暗い世相を少しでも明るくしたいということから、包装紙をアートでつくり上げました」(加藤さん)
プロジェクトはワークショップ開催の2年前からスタートしましたが、その初期の段階より、岡田さんには学習雑誌とタイアップしたいという思いがあったそうです。
「プロジェクト推進の先には、学習雑誌との付録企画を実施したいと。プログラムは監修に丸亀市猪熊弦一郎現代美術館、そして企画にはデザイナーの岡本健氏にも加わっていただき、考えに考え自信を持ってお届けできるものに仕上がっていったのですが、ワークショップで繋がれるお客様はどうしても限られます。そこで、私たちの取り組みをより広く多くの方に届けるために、『小学8年生』とのタイアップについて協議を進め、周囲のバックアップのもと、付録企画を実現できました。じつは『小学8年生』が創刊された頃、書店で拝見して、まずタイトルに惹かれ、学年に捉われず、『学びたい、知りたい』という気持ちに対して広く開かれたコンセプトを知って、いつかコラボレーションしたいと思っていました。今回の『包む文化』というテーマは、ぜひとも『小学8年生』さんとやってみたいという気持ちでした」(岡田さん)

誰もが達成感を得られるよう、付録の仕様を粘り強く調整
どういった付録にするかでは当初、包装紙をデザインする、シルクプリントで刷るなどの案もありましたが、「付録で何を伝えたいのか」を重視し、「包む」にフォーカスすることに。
「当時の編集長の明石さんが名古屋のワークショップに来てくださって、『やっぱり、包むという行為が大事ですよね』と。実際の授業を見学し、当社がこのプログラムでどのような思いを社会に還元したいのかということを、根底からしっかり汲み取ってくださったうえで、付録や特集ページをお考えいただけたのは嬉しいことでした」(岡田さん)
そこで、百貨店での贈り物の包み方である“斜め包み”ができる、折り方のガイド線が裏側に入った包装紙と、きれいに包めるサイズの専用箱を作成。完成までには多くの苦労がありましたが、子どもがうまく包めるよう、クオリティにはとことんこだわりました。
「うまく包めないとストレスを感じますし、付録を手にした読者の方に残念な気持ちにだけはなってほしくない。きれいに包めたときの達成感や、贈る相手を思い浮かべながらさらにきれいに包もうと思う気持ちに触れられるものになってほしいと考えました」(岡田さん)
「ワークショップでは原版をデザインしたら、その場で出力して箱を包むことまでやりましたが、出力はA4のコピー用紙なのですごく小さい箱しか包めないし、コピー用紙は固くてとても包みにくい。なかなかできない子もいて申し訳なかったのですが、それでも子どもたちは最後に『包めたー!』って盛り上がるんですよね。あの出来上がる喜び、達成感というものを付録で感じてもらいたいと、誰もがきれいに包める工夫をしました」(加藤さん)
とはいえ、百貨店の店頭では経験から身につけた感覚で包むため、改めてガイド線を入れる作業はかなり大変だったとのこと。
「紙を引っ張る手の力の強弱で違いが出ますし、箱の紙の厚みによっても微妙な差異が生じます。何度も繰り返し包んではガイド線や箱を微調整し、明石編集長にも何十回も来ていただきました。編集長を通じてデザイナーの方にお願いした小8バージョンの包装紙のデザインも、細かい修正を頼んだりして何度もトライしてもらいました。明石編集長をはじめスタッフの皆様には本当に粘り強く向き合っていただき、一丸となって取り組ませて頂いたからこそ、納得のいく付録にたどり着くことができたと思います」(岡田さん)

コラボによって伝えたいことが広く伝わり、社会的評価も獲得
付録企画の反響でまず嬉しかったのは、読者からの声でした。
「読者の方の感想を拝見して、私たちが伝えたかったことがこんなにもそのまま伝わるんだと驚きました。お子様からは『大人でも知らなかったきれいな包み方を知って、とても勉強になった』、保護者の方からは『今はエコのため包むことを省略しているが、包装紙で相手への敬意や思いやりを示すことができるとわかったので、必要に応じて使い、その意味を子どもへも伝えていく必要があると感じた』といった声が寄せられて、とても嬉しかったです。昨今は包装に対してマイナスなイメージもあり、当社でもスマートラッピングを推進していますが、包装をゼロにすることが果たして正しいのか? 贈り物はものを渡すだけの行為なのか? そうしたことを未来を担う世代に考えてもらうきっかけとして、まずは『包む』とはどういうことかを考える。それを読者の皆様と共有できたことに感動しました」(岡田さん)
「一番伝えたかったのは、相手を慮る気持ちが包み方で表現されているということ。『慮る』って今、日常生活では使わない言葉ですけど、大切にしたい日本文化ですね」(加藤さん)
コラボによって教育プログラムで伝えたかった思いを全国の読者に伝えることができ、SNSで話題になったことで、読者以外の方にも知っていただけたと思うとのこと。さらに日本雑誌広告賞の経済産業大臣賞受賞という快挙が社会的な広まりを後押ししました。
「雑誌の力、出版社さんの力と協業させていただいたことで、より多くの方々とのタッチポイントを得ることができ、成果を実感し、とてもいい取り組みだったなと思っていたところに加えて、そうした最高賞を頂戴することができたのは非常に光栄で、嬉しいの一言に尽きます。賞をとったことでさらに多くの人に知っていただくことができましたし、社内にも受賞の報告ができたことで、次に繋がることもあると思います」(岡田さん)
教育プログラムは文部科学省が主催する青少年の体験活動推進企業表彰「い〜たいけんアワード」の審査員奨励賞も受賞。今後も「コーポレートアイデンティティ」×「○○」の考え方でさまざまな取り組みを進めていきたいとのこと。
「今回の成果から、当社のアイデンティティと何かを掛け合わせることにより、大きな広がりを持たせることができるということを学びました。掛け合わせるものはいろいろあると思いますが、その掛け算のチョイスの一つとして『教育』はずっと残していきたいと思っています。アワードの際の文部科学省の方のお話からも、子どもに学校の勉強だけではなく、社会を生き抜く力を学ぶ機会をますます充実させたいという課題をお持ちで、企業がそれぞれ培ってきたものから子どもに学びを還元してほしいと思われているのだなと感じました。学習雑誌は昔から教育の門戸を広く開かれていますが、今後も小学館さまをはじめとした社外のプロの皆様との共創で、社会と繋がることのできるコンテンツを生み出したいと思っています」(岡田さん)
「今は本当に多くの企業さんが教育に取り組まれていて、こうしたことは企業文化というものが教育を通して社会への還元や貢献に繋がっていける、本当にいい取り組みだと思います。『8年生』という考え方は無限大ですとか、一つではないさまざまな視点を表していると思うんですが、そうした考え方の中で子どもは成長していくでしょうし、我々大人も、小学生は1年生から6年生までというような固定概念ではなく、『8年生』という概念を持つことで、何かすごく大きな広まりを得ることができるのではないでしょうか」(加藤さん)
今回のコラボレーションは、企業と学習雑誌の共創により、大きな成果と高い社会的評価を得ることができた好例といえます。学校の勉強にとどまらない「学び」が重要視されている中、『小学8年生』はこれからもさまざまな企業との付録企画を通して、子どもたちの好奇心を刺激し、可能性を広げていきます。

『小学8年生』の媒体資料ダウンロードはこちら: