『少年サンデー』気鋭の編集者が語るヒット漫画の舞台裏──小倉 功雅 第2回 伝道師・占い師・漫才師として作家に接する漫画編集者のあり方
2025/08/18
「面白さ」は、伝わらなければ意味がない。作家のネームに面白さの核がしっかりと存在しているなら、それを翻訳して届けていくのが漫画編集者の力だ。『古見さんは、コミュ症です。』『葬送のフリーレン』というヒット作を立ち上げてきた小倉功雅は、編集者の役割を「伝道師・占い師・漫才師」と表現する。第2回では、作品の面白さを伝え、見出し、届けていく編集力に迫る。
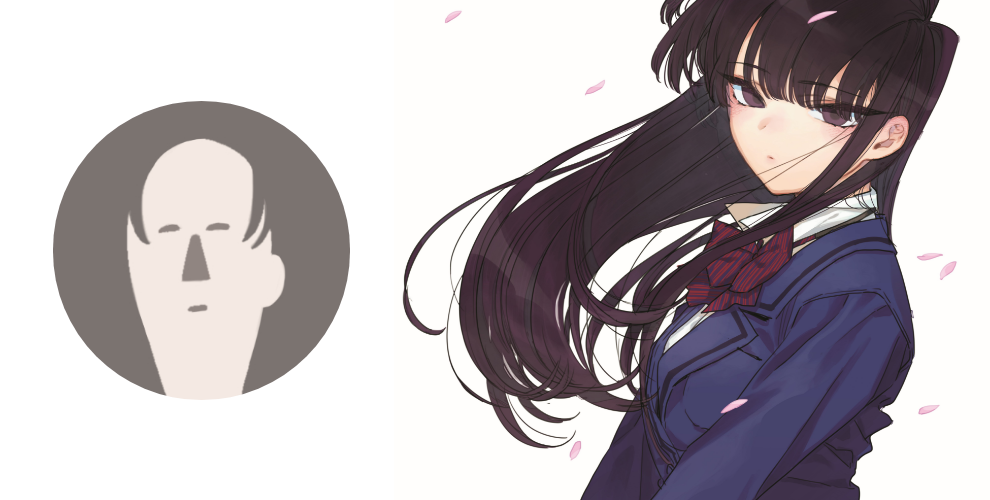
連載第1回はこちら
作家の面白さをどう「伝える」か──編集者の三つの役割
――前回は青山剛昌先生の現場で培った編集者としての基盤について伺いました。今回は、現在進行形としての小倉さんの編集スタイルについてお聞かせください。
僕は編集者の仕事には、大きく分けて三つの役割があると思っています。それは「伝道師」「占い師」「漫才師」です。
まず「伝道師」とは、作品の面白さをいかに読者に伝えるかという役割です。『週刊少年サンデー』も他の漫画誌と同様に、新人作家の発掘と育成を重視しています。新人さんの場合、打ち合わせでは「この人、本当に面白いことを考えているな」「このセリフ、めちゃくちゃいいな」と思うのに、いざネームや原稿になると、その面白さがうまく伝わらない、届いていないというケースが多くあります。そこで、直感で感じた面白さをどんな順番で描き、どんな構成にすれば届くか…を考える。そこに注力するのが、伝道師的な編集スタンスです。
――次に「占い師」とは?
作家さんの内面を読み解く役割です。作家さんが本当に描きたいことは何か、どんな表現が得意で、どこでつまずいているのか。まだ言葉になっていない段階から、それを汲み取っていく。そして、たとえば「このキャラクターのこの一言、読者に刺さります」とか「次にこういう展開だとしたら、読者の心に響くかもしれません」といったように、現在の分析と未来の予測をセットで提案する。それが「占い師」としての漫画編集者だと思います。
――そして最後に「漫才師」。これはやはり「しゃべる」力でしょうか。
そうですね。編集者って、やっぱり“しゃべる仕事”だと思っています。作家さんが力を入れた描写が伝わりきっていなかったり、逆に何気なく描いた部分がすごく良かったりすることがあります。そのとき「ここはもっと広げましょう」とか「このシーンは削ってもいいかもしれません」と伝える必要がある。そこで求められるのは、話す内容の精度です。その意味で「漫才師」にたとえました。
もちろん、ただの勘や感覚ではダメで、できるだけロジカルに、観察と分析に基づいて言語化すべきです。ここで、前回お話しした「XY軸のゼロ座標」、つまり「面白さのど真ん中」という視点が生きることもあります。最大公約数的な面白さの座標を起点として、その作品のどこがどの方向に、どのくらいズレているかを明解に説明できなければなりません。
作家さんが人生をかけて描いている作品に対して「ここを変えましょう」と伝えるわけですから、論理性だけではなく、相応の覚悟と作家さんへの敬意も欠かせません。「漫才師」には、ただしゃべるのではなく「伝え方のプロであること」も含んでいます。
――三つの役割を伺っていると、どれも「伝える」という編集の本質に通じるように感じます。
そうですね。これは宣伝や広告にも通じる話かもしれませんが、作品の魅力をどう届けるかは、編集者の表現力と設計力が問われる部分だと思っています。作品が持っている熱量を、できるだけ100パーセントの伝導率で読者に届けたい。編集という仕事に向き合ううえで、常にそこを意識しながら取り組んでいます。
編集者の論理と直感から生まれた、新たな「面白さ」
――作品の届け方を考える一方で、制作の現場ではどんな瞬間に手応えを感じますか?
やっぱり、打ち合わせを超えるネームに出会ったときです。プロの作家は、打ち合わせよりネーム、ネームより下絵、下絵より原稿と、工程を重ねるごとに面白さを積み上げていく。精度の上がり方には驚かされます。
『名探偵コナン』で安室透が初登場したとき「これは今まででいちばん面白い展開かもしれない」と感じたのを覚えています。作品の中に新しい風が吹いたような感覚がありました。

同じように、『古見さんは、コミュ症です。』や『葬送のフリーレン』でも、ネームが上がってきた瞬間に「これは今まででいちばん面白いかもしれない」と思うことが何度もありました。厳密には“いちばん”というよりも、打ち合わせでは明確に感じてなかったものが、ネームという形で、今までとは種類の異なる面白さ、精度へと高まった時に、感覚的に反応していたんだと思います。
――編集者としての客観性と、「これがいちばん」と思える直感。その往復も漫画編集者の醍醐味でしょうか。
そうですね。『葬送のフリーレン』の立ち上げに至る過程を例に挙げると、より実感があります。連載前に山田鐘人先生と取り組んだ『ぼっち博士とロボット少女の絶望的ユートピア』という作品は、個人的にはとても面白かったんですが、残念ながらセールス的には良い結果が出ませんでした。そこで「どうすればこの作家さんの漫画をもっと多くの人に届けられるか」を真剣に考えました。
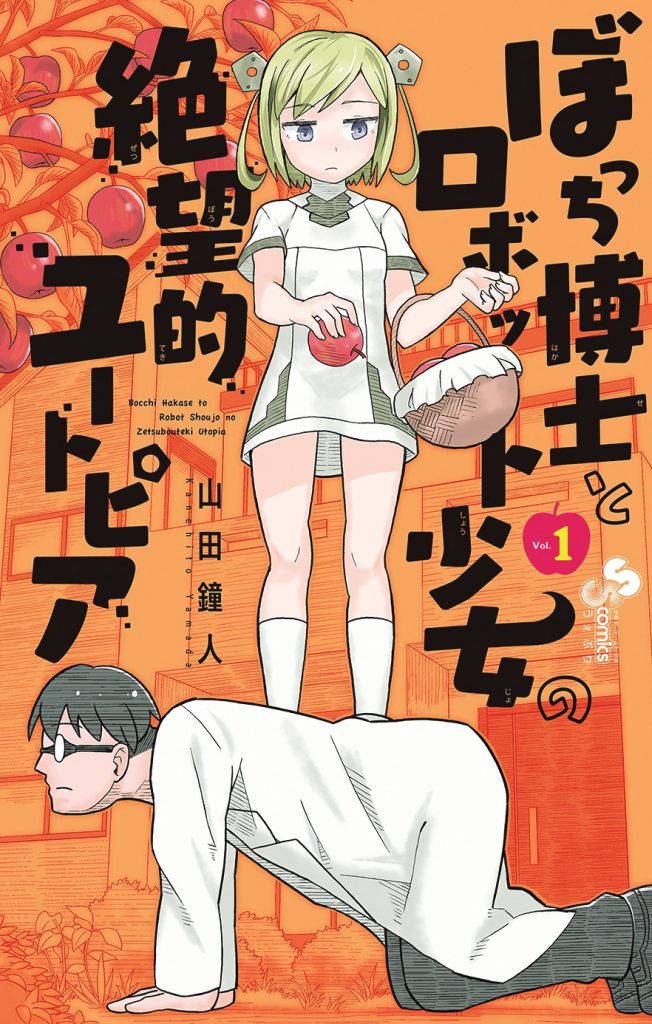
そのとき「作画を変えることで、可能性が広がるかもしれない」と思いました。慎重かつ誠実に山田先生と話し合い、ネーム原作というスタイルを提案しました。山田先生は漫画を描ける方ですから、ネームに特化していただくことで構成力やセリフの魅力がより際立つと考えたんです。
そして作画をお願いしたのが、アベツカサ先生。キャラクターデザインや絵の透明感、画面構成にずば抜けたセンスがあって、ビジュアル面での訴求力が高い作家さんです。先生が描いたフリーレンの姿には圧倒的な魅力があり、SNSやコスプレなどの広がりを見ても、愛されるキャラクターになっていることがわかります。

物語の力とビジュアルの力を合わせたとき「これなら面白さのど真ん中にいけるかも」という感覚がありました。でも、最初から計算づくで組み合わせたわけではなく「この二人が組んだ漫画を、まず自分が読みたい」と思ったのが出発点です。主観的な“読みたい”という気持ちを起点に「多くの人にも届くはず」と客観的に補強していく。そのプロセスが、僕にとっての編集作業の一つかもしれません。
「人間は変わらない」からこそ届く──編集者が信じる普遍と共感
──『葬送のフリーレン』も、そして担当されたもう一つのヒット作『古見さんは、コミュ症です。』も、ジャンルは違えど「コミュニケーション」がテーマのように思えます。SNSでの炎上や誤解といった時代的なテーマを意識しているのでしょうか?
キーワードとして捉えるなら、確かに「コミュニケーション」というテーマに共通点はあるかもしれません。ただ、『フリーレン』の山田先生も、『古見さん』のオダトモヒト先生も、それぞれが「こういうものを描きたい」とお話されて、僕自身もその方向性に深く共感し、賛同してスタートした企画です。時代性というよりも、作家さんが描こうとした“人間の本質”に寄り添った、というほうが正確かもしれません。
古代エジプトの壁画に「最近の若いやつは……」みたいな愚痴が書かれていたという有名な逸話があるじゃないですか。何千年も前から、人間って本質的には変わっていないんだなって思うんです。身近な人の死に直面したとき、誤解からくる苦しさ、人との摩擦──そういう「変わらない人間の感情」にこそ、物語としての普遍的な面白さがある感覚があります。
──「人間の本質を描く物語」という点から、『古見さん』はどのように立ち上がっていきましたか?
出発点は「コミュ症ってどうですか?」という打ち合せ中のオダ先生の一言です。タイトルに「コミュ症」と入れるのは、ネガティブに取られる危険性もあり、いろいろな意見がありました。が、結果、読者も作者の意図をきちんと受け取ってくださって、掲載開始時から嬉しい反応をたくさんいただきました。コミックス発売後、北米市場は好調でしたし、南米の読者の好意的な感想も目に留まりました。「コミュ症」というテーマが、国や文化を越えて共有される人間関係の悩みであることを、この作品を通じて強く感じました。

──これまでも語っていただいた“面白さのど真ん中”は、共感できる感情のど真ん中にも通じるということですね。
そうした共感できる部分があるからこそ、多くの人に刺さるのだと思います。だから僕は、流行を追うよりも、作家さんがあたためてきたテーマや、人間の本質から掘っていくアプローチを大切にしてます。
変わらないものを軸に物語を作っていくと、読者に届く確率は自然と上がっていく。正しいかはわかりませんが、そう考えている節があります。ヒット作って、「つくれる」とは決して言い切れないけれど、「読者に届く確率を上げること」はできる。それが、漫画編集という仕事の核心なんじゃないかとも思っています。
作家の内面に寄り添い、言葉を尽くして意図を届ける。小倉は、編集者の仕事を「伝道師・占い師・漫才師」と表現しつつ、そのすべてを貫く「翻訳者」としての視点を大切にしてきた。最終回では、漫画がIPとして広がる時代における、編集者の「届ける」「守る」信条に迫る。
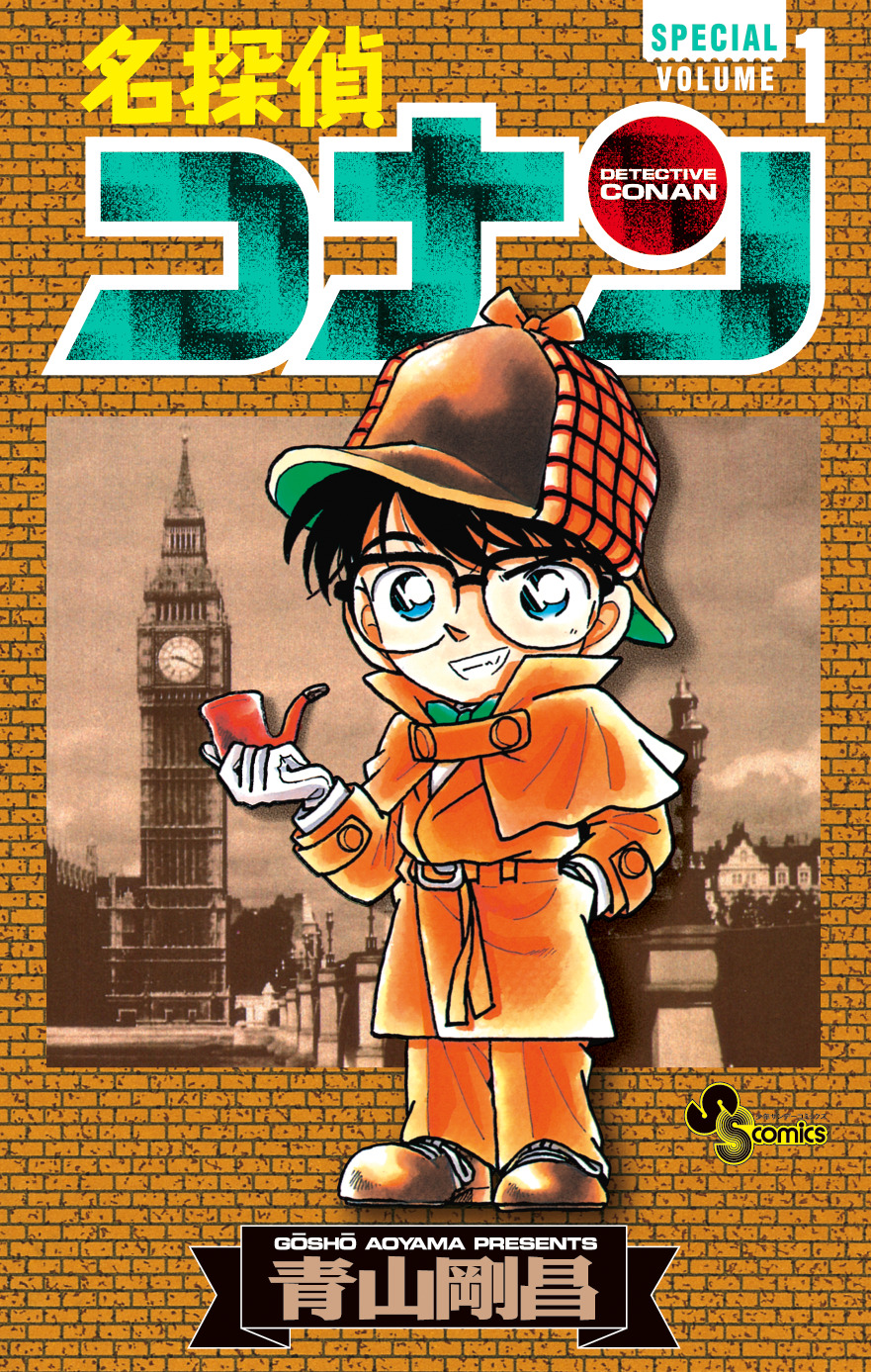
少年サンデーコミックス
『名探偵コナン』
作/青山剛昌
1~107巻発売中(以下続刊)
https://shogakukan-comic.jp/book?isbn=9784091233714

少年サンデーコミックス
『古見さんは、コミュ症です。』
作/オダトモヒト
全37巻発売中(完結)
https://shogakukan-comic.jp/book?isbn=9784091273437
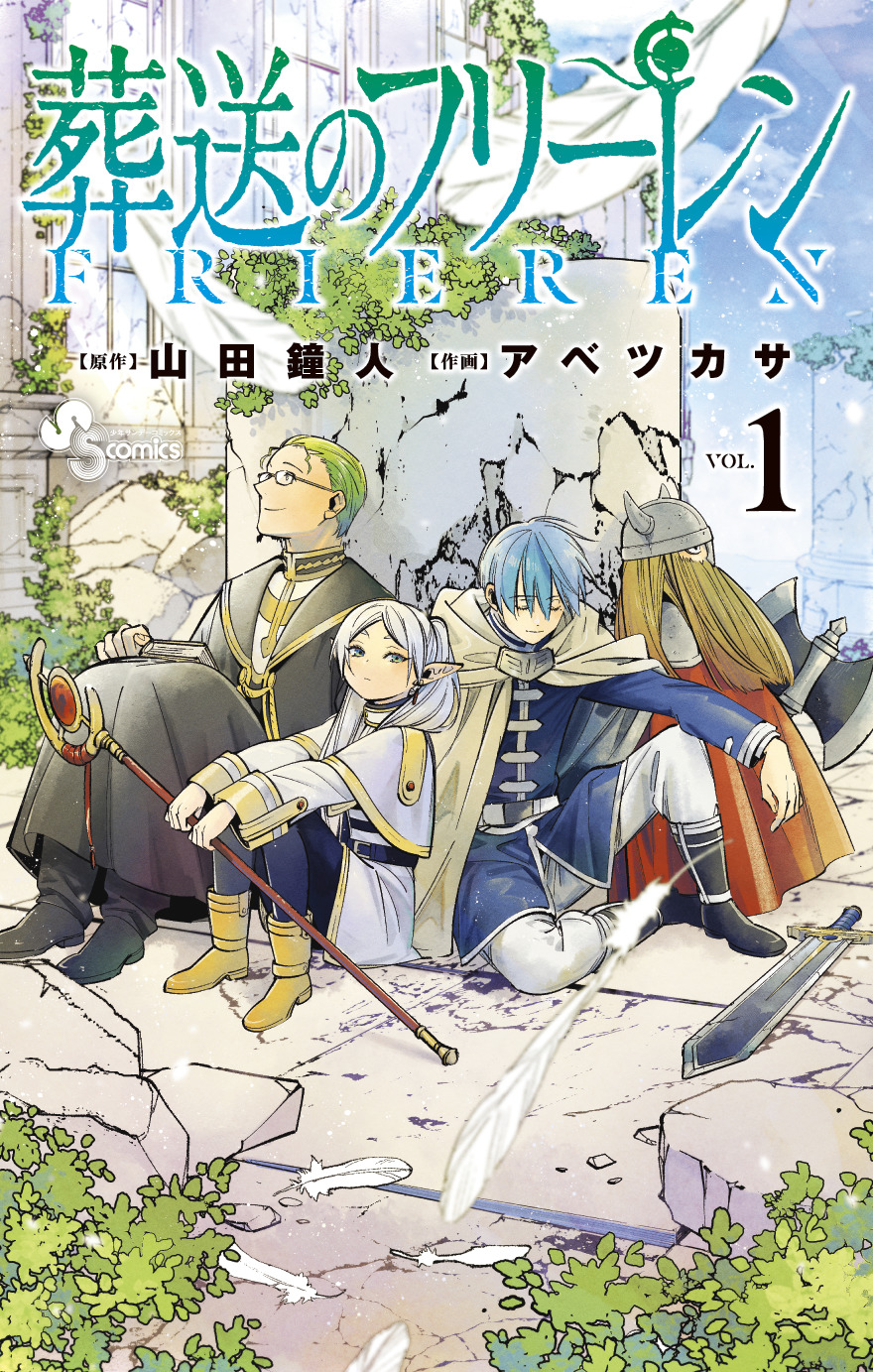
少年サンデーコミックス
『葬送のフリーレン』
作/山田鐘人 画/アベツカサ
1~14巻発売中(以下続刊)
https://shogakukan-comic.jp/book?isbn=9784098501809
第1回はこちら
最終回はこちら
『週刊少年サンデー』の媒体資料ダウンロードはこちら:








