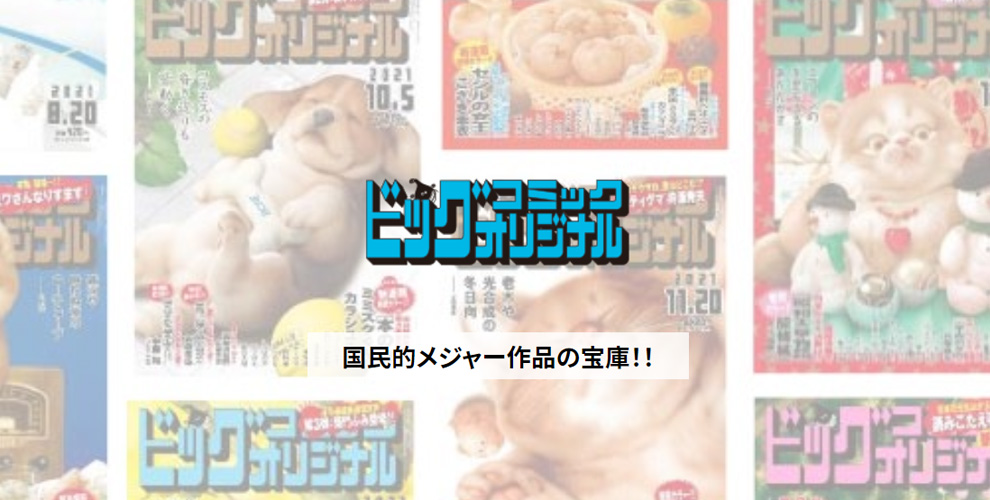変わらないために、変わり続ける――半世紀の信頼を土台に“今”の感性に応えます。 『ビッグコミックオリジナル』荻野克展編集長インタビュー
2025/04/14
作品が持つテーマ性から多くのコラボレーションの可能性が見えてきます
1997年に小学館に入社し『週刊ヤングサンデー』に配属。2008年『ビッグコミックスピリッツ』へ異動。両編集部で『アオアシ』『土竜の唄』『ソラニン』『アオイホノオ』などの人気作品を立ち上げる。その後、『週刊少年サンデー』『サンデーGX』を経て『スピリッツ』に復帰し、2022年より『ビッグコミックオリジナル』編集部へ。編集長代理を務めた後、2024年10月より現職。

“生活の一部”として愛されてきた信頼感。これからも新たな読者へ届けていきたい
『ビッグコミックオリジナル』(以下『オリジナル』)の“雑誌としての強み”は、どんなところにあるでしょうか?
「それはなんと言っても「歴史」です。2024年に創刊50周年を迎えたこの雑誌が、これほど長く読者に支持され続けてきたという事実は、漫画雑誌において並大抵のことではありません。
編集長に就任して改めて実感したのは、その“歴史”が生み出す“安定感”です。自分自身も、まずはその安定感に助けられてきたと感じています。読者の皆さんからは日々、読者ハガキやアンケート、時にはお電話というかたちで反応が届き「生活の一部として読んでいる」という声も少なくありません。なかには「家族が亡くなったとき、愛読していた『オリジナル』を棺に納めた」というエピソードまで寄せられ、雑誌が人の人生に寄り添っていることの重みを痛感しました。
こうした、“雑誌そのもの”を長く愛してくださる読者の存在こそが『オリジナル』の最大の支えであり、弊社の青年漫画誌として今なおトップの発行部数を維持できている理由だと確信しています。
そしてもう一つ、『オリジナル』の顔として欠かせないのがイラストレーター・村松誠さんによる表紙イラストです。1979年から描き続けられている犬や猫のイラストは、リアルで繊細、それでいてどこかユーモラスな表情を持ち、見る人の心をふっと和ませてくれるもの。見た瞬間に「あの絵だ」と分かるほど、雑誌の象徴として親しまれています。
このように、安定感を築いてブランドを確立できている『オリジナル』ですが、雑誌は今“過渡期”にあります。これまで大切に受け継がれてきた長期連載や定番作品を守ることはもちろん、新たな読者に向けて、新しい風をどう吹き込んでいくか。就任後の数か月は“雑誌の空気”と“読者の温度”を感じ取り、作家さんと一人ひとり向き合うことを重視してきました。これからはその土台の上に、次の時代へとつながる『オリジナル』をつくっていくフェーズに入っていきたいと考えています。」
編集長として考える『次のフェーズ』のイメージを教えてください。
「『オリジナル』の大きな魅力のひとつは、誰もが知る長期連載の存在です。西岸良平先生の『三丁目の夕日』は50年超、やまさき十三先生・北見けんいち先生の『釣りバカ日誌』も45年以上続いており、まさに“宝物”のような作品群です。弘兼憲史先生の『黄昏流星群』は2025年に連載30周年を迎え、記念イヤーとしての新たな展開も模索しています。また安倍夜郎先生の『深夜食堂』も2026年に初掲載から20周年を迎える節目となり、今後の展開に期待が高まっています。
こうした長寿作品を大切にしながら、一方で“新しい作品を育てること”も編集長としての重要な使命だと感じています。連載歴の若い作品では、東村アキコ先生の『まるさんかくしかく』や長尾謙一郎先生の『バックホームブルース』に注目しています。また、コミックス10~20巻前後の中期作品には、こざき亜衣先生の『セシルの女王』、能條純一先生の『昭和天皇物語』などがあり、どちらも電子書籍でのダウンロード数が伸びていて、連載が進んでも勢いを保っているのが特徴です。これは非常に頼もしい兆しであり、次代の『オリジナル』を支える柱と見ています。長期・中期・始まりたてという3つの作品軸をバランスよく育てながら、雑誌としての厚みと多様性をさらに広げていきたいと考えています。
『オリジナル』には「社会派作品が多い」という印象を持つ方もいるでしょう。社会性の高い作品が増えてきた背景には、現代の閉塞感や課題意識があると思います。高齢化社会と老人ホームの闇を描いた山本おさむ先生の『れむ a stray cat』のように、社会の現実を浮き彫りにすることは、漫画のひとつの役割でもあります。
その一方で、私は“読後感の明るさ”も同じくらい大切にしたいと思っています。たとえテーマがシリアスであっても「読んで元気になれる」「クスッと笑える」、そんな感触を持ってもらえる作品を届けたい。読者の多くが、漫画に「ホッとできる時間」や「ちょっとした癒し」を求めていると感じるからです。だからこそ、作家の皆さんと方向性を共有しながら、読後に前向きな気持ちになれるような作品づくりを進めることが「次のフェーズ」になると思っています。」
変わらないために変わり続ける――新たな読者に向けて
雑誌として今、どのような読者層への向き合い方が求められていると感じていますか?
「最も大きな課題は「長年支えてくださっている読者」と「これから新たに取り込みたい若い世代」、その両方に向けた誌面づくりを、どう両立させていくかという点です。特に紙媒体を中心に購読されているシニア世代の方々には、非常に強い支持をいただいており、その信頼を裏切るような急激な路線変更は避けなければなりません。一方で、電子市場の成長やSNSの影響力が高まる中で、若い読者へのアプローチも無視できない課題になっています。このバランスをとることが、編集部として常に頭を悩ませているところです。」
その課題に対し、どのような工夫や戦略を考えていますか?
「まずは、既存の読者の期待を損なうことなく、新たな読者層へと広げていく。そのために、SNSやネットを活用したプロモーションはもちろんですが、最終的に雑誌の“核”となるのは、やはり漫画そのものの力だと思います。
とりわけ重要なのは「題材の選び方」です。50~70代の読者と、30~40代の読者が共通して関心を持てるテーマは何か? 編集部内では、日常的にその話し合いを重ねています。例えば食やスポーツなどは、世代を超えて共感を呼びやすい題材です。そこにどんな切り口を加えるかで、作品の広がり方が大きく変わってきます。」
読者の世代が多様化する中で、編集部としてどのような意識を持っていますか?
「気をつけているのは、過去のイメージや固定観念にとらわれないことです。例えば「シニア=時代劇が好き」という発想も、今となっては一面的かもしれません。令和の50代、60代、70代の方々の中には、アニメや最新カルチャーに明るい方も多く、旧来の“シニア像”とは異なる側面を持っています。だからこそ、編集部では「世代を超えて共鳴できるテーマ」や「意外な接点」を探る姿勢が大切になってきます。今後は、そういったテーマを掘り下げながら、どの世代の読者にも届く、懐の深い雑誌として「変わらないために、柔軟に変化し続けること」――それが『オリジナル』に求められている姿勢だと考えています。」
“人間ドラマ”を軸に、信頼あるコラボレーションを
『オリジナル』ならではの共創の可能性について、どうお考えですか?
「編集部としても「なんでも挑戦したい」という思いは強く持っています。以前、私が『ビッグコミックスピリッツ』で小林有吾先生のサッカー漫画『アオアシ』を立ち上げた際には、映像化やメディア展開によって作品の世界が大きく広がり、それまで届かなかった層にリーチできたという実感がありました。企業からの連携のお声がけも多く、作品の可能性を広げていくことの価値を、身をもって感じました。
『オリジナル』でも同じように、作家さんが描く世界を軸に、共鳴してくださる企業やブランドと一緒に新しい共創ができたらと考えています。そこにあるのは、あくまで作品世界へのリスペクト。それが共創のスタート地点になると思っています。」
すでに実績のある事例もあるようですね。
「『セシルの女王』では、イギリス王室を描いた世界観と、人気ミュージカル『SIX』との親和性から、タイアップ企画を展開しました。『黄昏流星群』では、弘兼先生の地元である山口県の蔵元・旭酒造さんとのつながりで、人気の日本酒『獺祭』プレゼントキャンペーンを実施したこともあります。
『釣りバカ日誌』も、長年にわたり社会やサラリーマン文化を描き続けており、企業との相性も良い作品です。作品に込められた“人間ドラマ”や“人生の機微”が、企業やサービスの価値観とリンクすれば、自然な形でのコラボレーションが可能になると考えています。」
読者層とのマッチングという意味でも、強みはありそうです。
「『オリジナル』は年齢を問わず知的好奇心が高く、非常にアクティブな読者が多いんです。70代で大学に通っているという方もいますし、社会や歴史を深掘りするテーマへの関心も高い。そうした読者の特性は、たとえば旅行会社とのコラボ企画などにもつながる可能性があります。
実際「『まるさんかくしかく』を読んで、家族で宮崎旅行に出かけた」という声が届いたこともあり、作品の舞台をめぐる“体験型”の企画――いわゆる聖地巡礼的な発想も現実味を帯びてきています。他にも『れむ a stray cat』と終活関連のサービスを掛け合わせたり、医療現場を描いた『看護助手のナナちゃん』を通じて病院・製薬企業との連携、さらに長年『オリジナル』の顔として親しまれてきた村松誠先生の動物イラストを活かしたペット業界とのコラボレーションなども面白い展開になりそうだと感じています。幅広いテーマ性を持つ作品が多い『オリジナル』だからこそ多くのコラボレーションの可能性が見えてきます。」
時代に合わせたテーマ設定や新たな分野への広がりについてはいかがですか?
「マッチングアプリなど、かつては描かれにくかったテーマも、今では一般的な題材として成立しています。読者の日常に即した“今どきのリアル”をどう漫画に反映させるか。そして、そこからどんな社会との接点を生み出せるか――編集部としても強く意識している部分です。
『ビッグコミックオリジナル』は、レジェンド作品と上質な読者層を抱える媒体として、信頼性の高いパートナーシップが築けるはず。今後も、作品の世界観を社会に橋渡しする“共創”を、編集部から積極的に仕掛けていきたいと考えています。」
荻野編集長の漫画愛の原点は、少年時代にあります。インターネットもなかった当時、古本屋を巡って藤子不二雄作品のレアなタイトルを探し出すのが何よりの楽しみだったそうです。雑誌では『コロコロコミック』から『少年サンデー』『少年ジャンプ』などの少年誌を経て、青年誌へと自然にステップアップ。特に『あぶさん』(作/水島新司)には強く惹かれ、「二日酔いでも決めるときは決める」というダンディズムに深く影響を受けました。2014年まで41年間にわたり『オリジナル』に連載されたこの長寿作品を仰ぎ見ながら、次なる“宝物”を探しています。
プライベートでは、趣味は「広く浅く」。ギター、バイク、写真、料理…と精力的に挑戦するものの「不器用で、なかなか続かないのが悩み」と笑います。家庭でも、子どもたちが好きな漫画やアニメに興味を持ち、積極的に触れているとか。「子どもやその友だちが“知ってる!”と言ってくれる作品を生み出したい」と語る荻野編集長。そんな等身大の目線が、雑誌づくりにもナチュラルに反映されているようです。
『ビッグコミックオリジナル』の媒体資料ダウンロードはこちら: